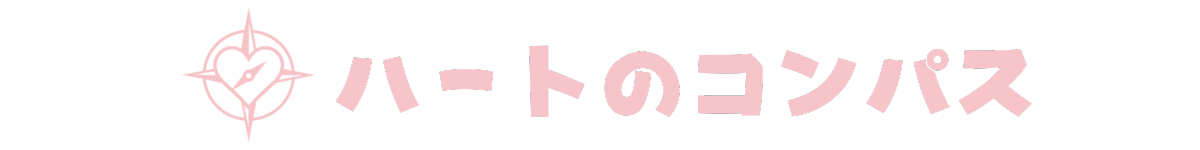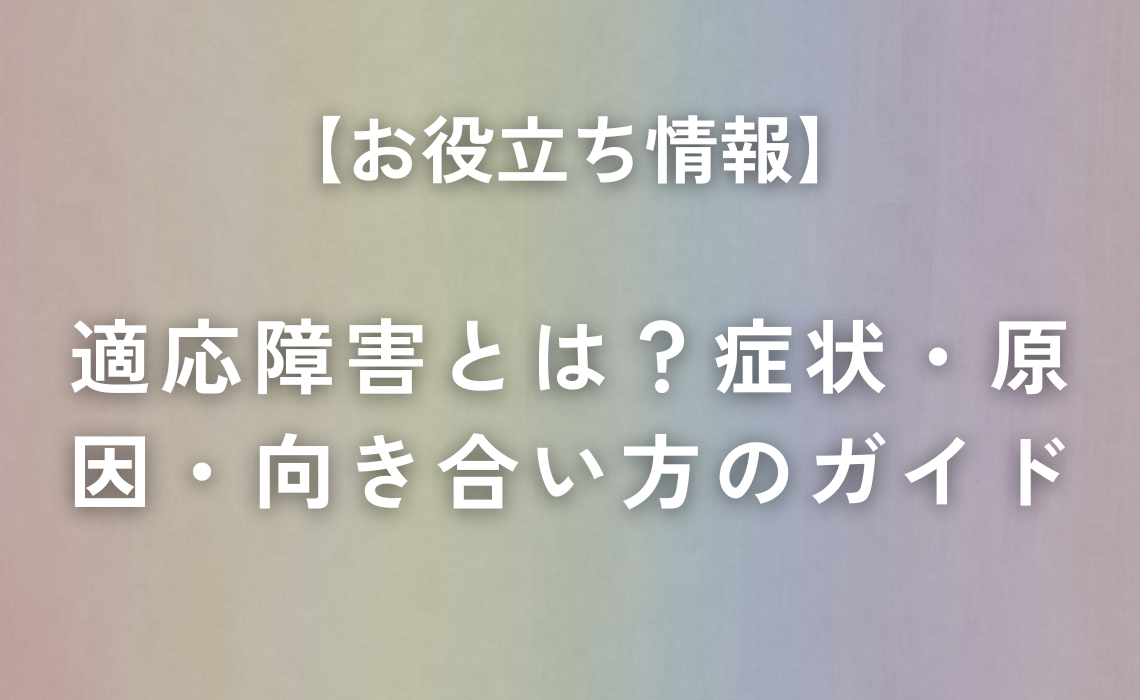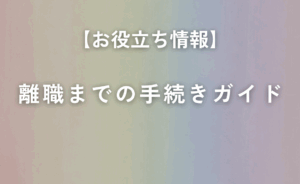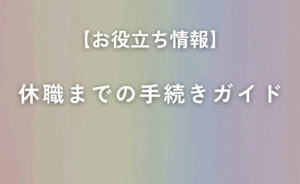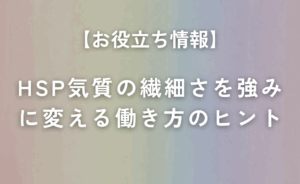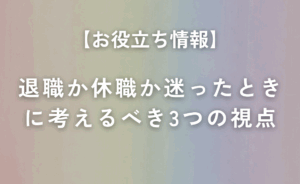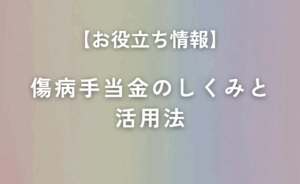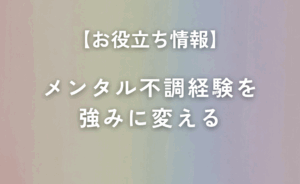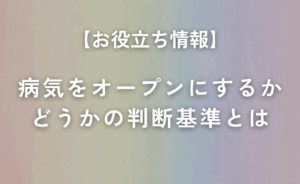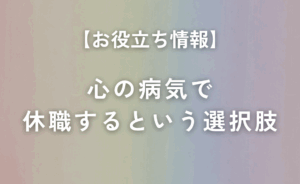適応障害とは?症状・原因・向き合い方のガイド
働いている人や学生の中には、環境の変化や強いストレスがきっかけで心身に不調をきたすことがあります。
その代表的なものが「適応障害」です。ここでは、適応障害の基本的な理解から、症状・原因・治療・生活上の工夫まで詳しくまとめます。
1. 適応障害とは?
適応障害は、生活や職場、学校などの環境変化にうまく適応できず、強いストレス反応として心や体に症状が現れる状態を指します。
国際的な診断基準(DSM-5など)でも「明らかなストレス因子があり、その影響で生活や仕事に支障が出ていること」が特徴とされています。
2. 主な症状
精神面の症状
気分の落ち込み、不安、焦燥感、イライラ、無力感など。
身体面の症状
頭痛、胃痛、食欲不振、倦怠感、動悸、睡眠障害など。
行動面の変化
欠勤や遅刻の増加、集中力の低下、人間関係の回避など。
ポイント
うつ病と似ていますが、ストレス因子がはっきりしている点が特徴です。
3. 適応障害を引き起こす原因
職場の環境変化
部署異動、上司や同僚とのトラブル、過剰な業務量など。
生活上の変化
結婚、出産、転居、介護、進学など。
対人関係のストレス
いじめ、パワハラ、家庭内の不和など。
4. 診断と治療方法
診断
精神科や心療内科で医師による問診・カウンセリングを通じて行われます。
治療の基本
ストレス因子からの距離を取ることが重要。休職や生活環境の調整が推奨される場合もあります。
薬物療法
必要に応じて抗不安薬や睡眠薬が処方されることがあります。
心理療法
認知行動療法やカウンセリングで、考え方や行動パターンの改善を目指すこともあります。
5. 日常生活でできる工夫
休養をしっかり取る
心身をリセットすることを最優先にしましょう。
生活リズムを整える
睡眠・食事・運動の基本を意識するだけでも改善につながります。
サポートを受ける
家族、友人、専門家、産業医、カウンセラーなどに相談することが回復への近道です。
無理をしない
「頑張らなきゃ」と自分を追い詰めず、少しずつできることから始める姿勢が大切です。
6. 職場や学校との関わり方
産業医や人事に相談し、勤務の調整や休職制度を活用することができます。
学校では保健室や学生相談室を頼ることも有効です。
大切なのは「一人で抱え込まないこと」。サポートを活用することは決して甘えではありません。
まとめ
適応障害は「心が弱いから」なるのではなく、誰にでも起こり得るストレス反応です。
適切に診断を受け、ストレス因子から距離を取り、休養とサポートを活用すれば回復は十分可能です。
大切なのは、早めに相談し、一人で抱え込まないことです。