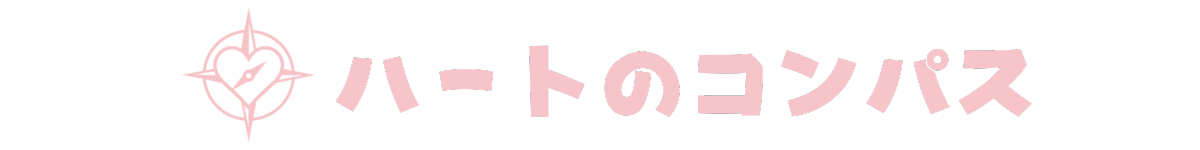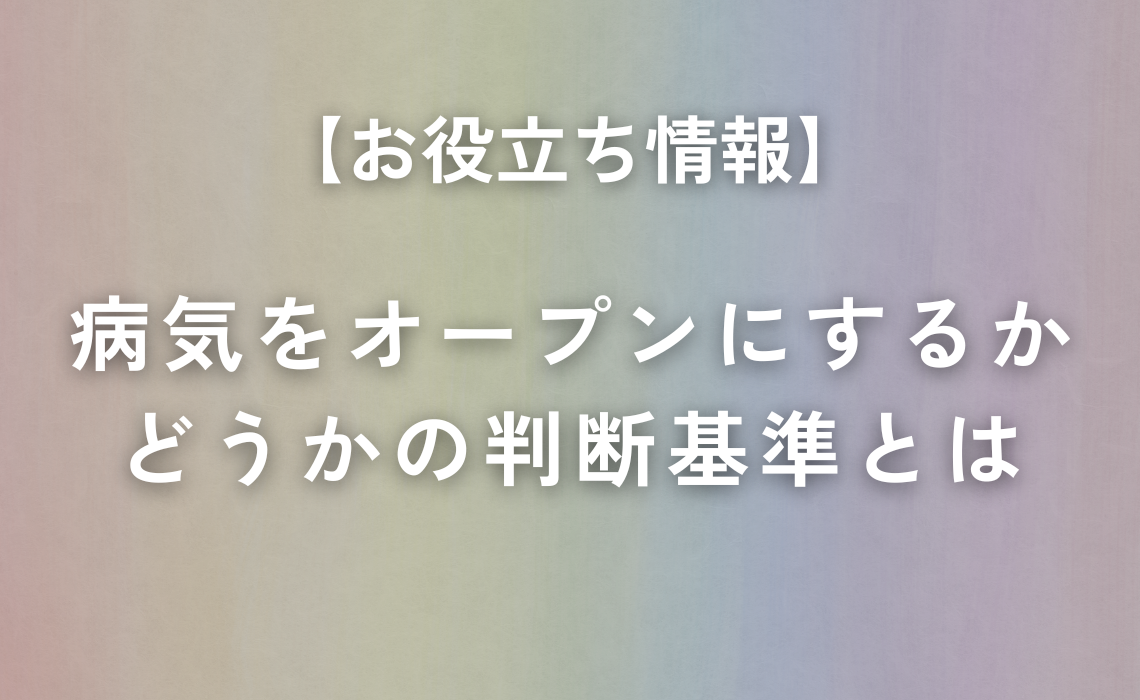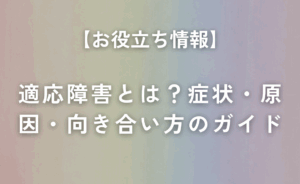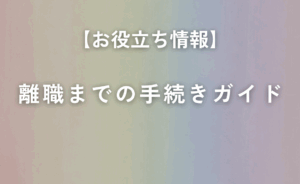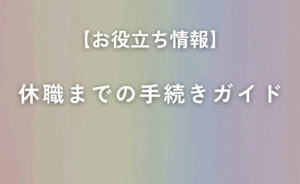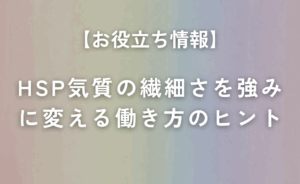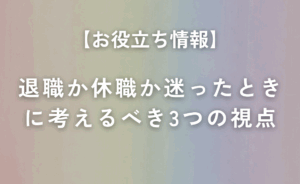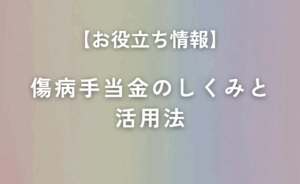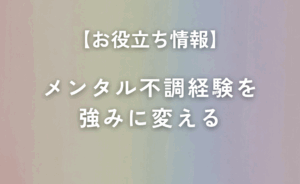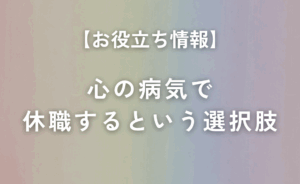病気をオープンにするかどうかの判断基準とは
心の病気を抱えているとき、自分の状態を周囲にどこまで伝えるべきか、あるいはそもそも伝えるべきかどうかという判断は、多くの人にとって大きな悩みです。特に職場や学校、家庭などの人間関係においては、その告白がどのような影響を及ぼすのか不安に感じる方も多いでしょう。
この記事では、心の病気を「オープン」にするかどうかを考える際に役立つ判断基準や注意点について、信頼できる情報に基づいて丁寧に解説します。
なぜ病気をオープンにするか悩むのか
心の病気を周囲に打ち明けることは、身体の病気に比べて社会的なハードルが高い傾向にあります。その背景には、以下のような要因があります。
- スティグマ(偏見):うつ病や不安障害などの心の病は、未だに偏見や誤解が根強く残っており、偏見を受けるのではないかと不安になる人が多いです。
- 理解の乏しさ:周囲に心の病についての正しい理解がないと、かえって状況が悪化する場合もあります。
- 仕事や学業への影響:「病気を打ち明けたことで評価が下がるのでは」といった不安も、オープンにすることへのブレーキになります。
このような背景があるからこそ、オープンにするかどうかの判断は慎重に行う必要があります。
判断基準① 信頼できる相手かどうか
最初に考えるべきは、「その相手が信頼できるかどうか」です。オープンにすることでサポートが得られる一方で、場合によっては逆効果となることもあるため、相手の性格や態度を見極めることが重要です。
- 普段から話をよく聞いてくれる人
- 他人の秘密を守る信頼性のある人
- 心の病について偏見のない人
このような特徴を持つ人であれば、安心して打ち明けることができる可能性が高いでしょう。反対に、無理解や無関心を感じる相手には無理に話す必要はありません。
判断基準② オープンにする目的を明確にする
「なぜオープンにしたいのか」「何を期待しているのか」という目的を明確にすることも大切です。以下のような目的がある場合、伝える意義は高いといえます。
- 職場での配慮や合理的配慮を得たい
- 家族や友人にサポートしてもらいたい
- 心の病を隠すことに疲れた、精神的負担を減らしたい
目的がはっきりしていれば、どのように話せば良いかも見えてきますし、相手の反応に対しても冷静に対応できるようになります。
判断基準③ タイミングと環境の整備
打ち明けるタイミングや場所も、心の病をオープンにする上で非常に重要です。伝えることで誤解や混乱が生じないよう、冷静な状況を選ぶようにしましょう。
- 相手が落ち着いて話を聞ける状況であること
- プライベートな環境で、周囲に聞かれないようにすること
- ご自身の体調が安定しているタイミングを選ぶこと
また、職場で伝える場合には、産業医や人事担当者を通じて話すという方法もあります。直接上司に言いにくい場合は、第三者のサポートを利用するのも良い選択肢です。
判断基準④ 法的・制度的な観点を知っておく
日本では、障害者差別解消法や労働法に基づいて、心の病を抱える人に対する合理的配慮が義務付けられています。したがって、必要なサポートを受けるためには、自分の病気について伝えることが必要な場面もあります。
特に以下のようなケースでは、オープンにすることでメリットが生じやすいです。
- 就労支援や配慮を受けるために、障害者雇用制度を利用する場合
- 学校で特別支援教育の対象となる場合
- 公的支援や制度の利用を検討している場合
法制度を知ることで、「伝えるべきかどうか」を客観的に判断できる材料になります。
無理にオープンにする必要はない
最後に強調したいのは、「必ずしも病気をオープンにする必要はない」ということです。話すことで得られるサポートがある一方で、まだ社会的な偏見が存在していることも事実です。自分を守ることも、心の健康を保つ上で重要な判断です。
- 「今は話さない」と決めることも、立派な選択肢です
- 信頼できる専門家(カウンセラーや精神科医)にだけ話すという方法もあります
- 時間をかけて、少しずつ信頼関係を築いた後に話すのも有効です
どの選択が自分にとって一番安心できるかを軸に判断することが、何より大切です。